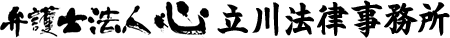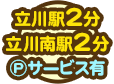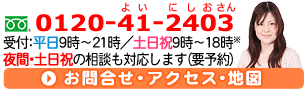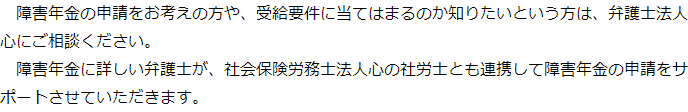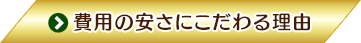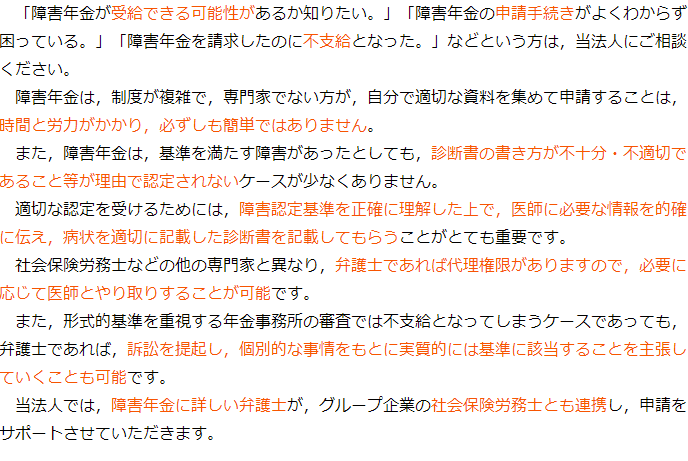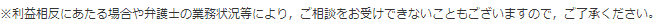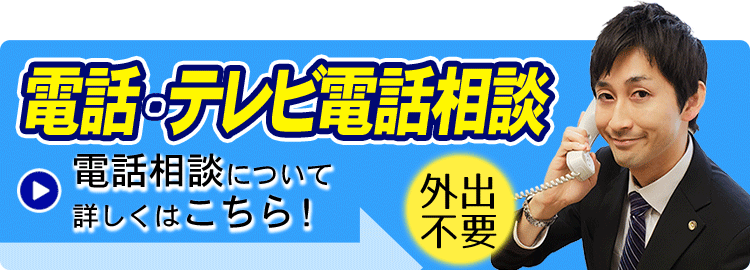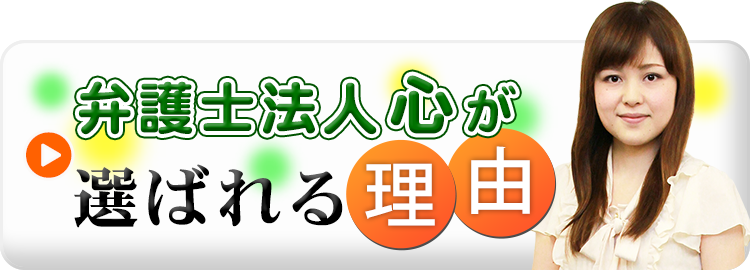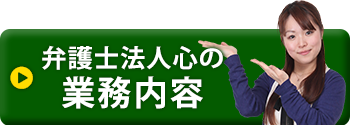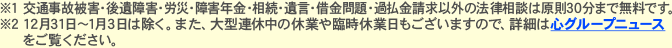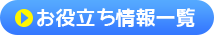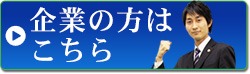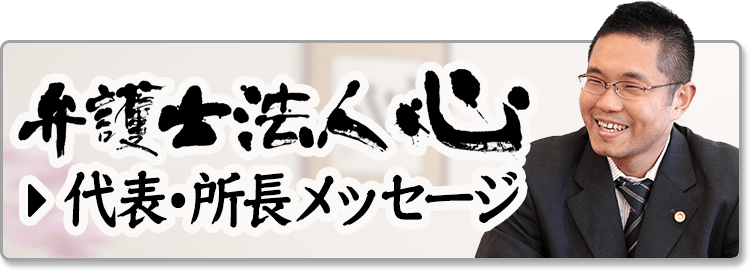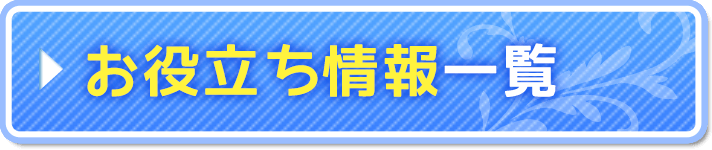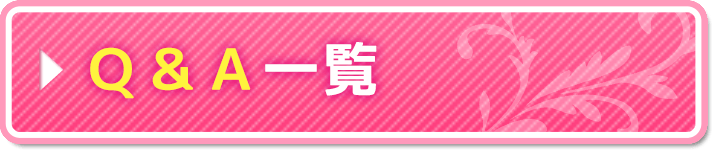障害年金
働きながら障害年金を受給できるケース
1 仕事と障害年金

障害年金は、病気や怪我が原因で日常生活に支障が生じたときに受給することができる年金です。
障害年金は、障害が原因で働くことができなくなってしまった方の生活を保障するための制度と考えられているため、働くことができていれば受給できないと考えている方もおられます。
しかしながら、障害年金は、受給要件さえ満たせば、働きながらでも受給することができます。
2 身体的な障害
障害年金の対象となる障害のうち、身体的な障害は、障害年金の対象となる基準が具体的な数値で決まっていることが多いです。
例えば、両眼の視力(矯正視力)がそれぞれ0.03以下の場合は1級、それぞれ0.07以下の場合には2級に該当しますし、一下肢を足関節以上で欠く場合には2級、リスフラン関節以上で失った場合には3級と定められています。
ご本人の傷病の状態がこれらの認定基準に達している場合、就労状況にかかわらず、障害年金の支給を受けることができます。
3 精神の障害
一方、精神の障害の障害年金の認定を受けるにあたっては、就労状況は大きな影響があります。
障害年金の対象となる精神の障害としては、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」がありますが、認定基準において、1級は「日常の用を弁ずることができない程度のもの」、2級は「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」、3級は「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と定められています。
この基準だけからみると、労働に著しい制限がなければ3級が認められず、それより重度の障害である2級以上は、働きながら受給することはできないように思えます。
しかしながら、就労している方でも、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を考慮して、障害年金が受給できることがあります。
例えば、障害者雇用や、就労継続支援A型・B型事業所で働いている場合、一般雇用であっても障害があることについて業務内容や就労時間を配慮してもらっている場合等です。
4 働きながら障害年金を受給したい方は弁護士法人心へ
当法人では、障害年金に関するご相談を多数いただいており、働きながら申請する場合のノウハウも豊富です。
立川にお住まいの方は、当法人までお問い合わせください。
障害年金の申請を依頼する専門家選びのポイント
1 障害年金の申請をサポートする専門家について

障害年金の申請をサポートする専門家として、主に弁護士と社会保険労務士が挙げられます。
弁護士や社会保険労務士の業務範囲は広いため、すべての弁護士や社会保険労務士が障害年金の申請に精通しているわけではありません。
弁護士事務所や社会保険労務士事務所によっても、特に力を入れている業務分野が異なることがあります。
そのため、障害年金の申請を依頼する場合は、障害年金の分野に特化し、経験と知識を持った専門家を選ぶことが重要です。
専門家を選ぶ際には、その人の専門分野や経験をよく調べ、適切なサポートを受けられるかを検討する必要があります。
2 適切な弁護士や社会保険労務士を見つける方法
では、障害年金の申請に精通した弁護士や社会保険労務士はどのように見つければよいのでしょうか。
多くの場合、障害年金を申請する方々は、医療機関や介護施設との接点があるため、そうした場所からの紹介や、実際にサービスを利用した人々の口コミを参考にする方法が考えられます。
また、医療機関や介護施設から紹介が得られない場合、インターネットを活用する手段もあります。
多くの弁護士事務所や社会保険労務士事務所は自らのホームページを持っており、そこには取り扱っている業務分野についての情報が掲載されています。
これらのホームページを閲覧し、障害年金の申請に関する経験や知識が豊富な事務所を探すことができます。
特に、障害年金に関して積極的に取り組んでいる事務所では、その分野に関する豊富な情報をホームページ上で提供していることが多いです。
そうした情報を参考にしながら、自分にとって適切なサポートをしてくれる事務所を選ぶと良いでしょう。
3 私たちにご相談ください
当法人には、障害年金の申請に精通した弁護士、社会保険労務士が多数在籍しております。
障害年金の申請でお困りの方は、ぜひ一度、お問い合わせください。
障害年金が受給できる場合とは
1 障害年金の受給要件

障害年金が受給できる場合というのは、障害年金受給に必要な各要件を満たしている場合と言い換えることができます。
障害年金の受給要件は、基本的に、①初診日の特定、②保険料の納付、③障害状態の3つに分けられます。
以下で、各要件について順番に説明します。
2 初診日の特定
障害年金の受給のためには、原則として初診日が特定されている必要があります(過去の1時点の通院の事実を示せば足りる場合や、一定期間内の通院の事実まで示せば足りる場合といった例外もあります。)。
この「初診日」は、申請しようとする傷病について最初に医療機関を受診した日のことです。
長く通院をしていて病院を転々としているケース等ですと、最初に通院した病院を覚えていないこともあるかと思いますし、覚えていたとしてもカルテが破棄されていて初診日の特定に至らないこと等もあります。
初診日は、制度上障害基礎年金か障害厚生年金か、保険料納付要件を満たしているかといった判断の基準となる重要な時点とされているため、初診日特定の要件を満たしていないとどんなに重い障害状態にあるとしても障害年金の受給は認められません。
3 保険料の納付
障害年金も年金制度の一種であり、原則65歳から受給開始となる老齢年金と同様、年金保険料を納付していることが基本的な前提となります。
老齢年金と異なるのは、初診日の属する月の前々月までの納付状況で受給の可否を判断される点と、要件を満たさない場合には受給自体認められないという点です。
例えば、2020年2月3日が初診日だったとすると、2019年12月分までの保険料の納付状況を、初診日前日の2020年2月2日時点を基準に判断します。
直近1年間の未納がない場合(上記の例では2019年1月分から12月分まで一度も未納月がない場合)、あるいは全被保険者期間を通じて1/3以上未納がない場合(納付開始から2019年12月分までで1/3以上未納がない場合)に要件を満たすものとなります。
4 障害状態
上記の2要件を満たしており、かつ、日本年金機構が定める障害の状態にあると判断された場合に障害年金が受給できることになります。
障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金の場合は加えて3級と、一時金の支給となる障害手当金の受給可能性があります。