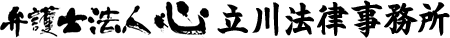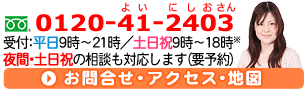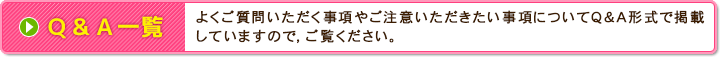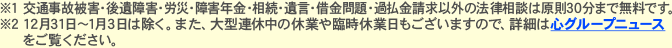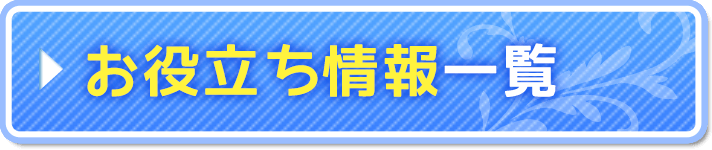特別受益とは?対象範囲・遺産分割時の対処法をわかりやすく解説
被相続人から生前贈与を受けるなど、財産上優遇されていた相続人は「特別受益」があると判断される可能性があります。
特別受益については、法定相続分の計算と遺留分の計算とで、一部異なる考え方をとる必要があります。
この記事では、遺産分割時に問題となる特別受益の範囲・計算に関するルールや、特別受益に関する遺産分割時の対処法などについてわかりやすく解説します。
1 特別受益とは?
まずは、遺産分割における「特別受益」の概要・特別受益者の範囲・特別受益の対象となる贈与について、基本的な知識を解説します。
⑴ 特別受益は遺産分割で相続人間の公平を図るルール
特別受益は、被相続人から相続人に対して特別に行われた遺贈または贈与を意味します。
たとえば相続人が、被相続人から多くの財産を贈与されたり、生活費の援助を受けたりしたようなケースでは、被相続人が、その相続人のために生前に財産を費やしたことで、結果的に相続財産が減少し、他の相続人が影響を受けていると考えることができます。
このような場合には、共同相続人間の不公平感を軽減するために、特別受益のある相続人の相続分・遺留分を減らすことで、共同相続人間の利害調整が図られます。
⑵ 特別受益者になり得る者の範囲
特別受益は、法定相続人間での相続における不公平を軽減するための制度です。
したがって、特別受益者になり得るのは基本的に相続人に限られます。
たとえば、被相続人のおじ・おば・いとこ・子の配偶者(婿・嫁)などは、法定相続人とならないため、原則として特別受益者にはなりません。
また、配偶者と子が相続人の場合には、後順位の相続人である祖父母や兄弟姉妹も特別受益者になることはありません。
⑶ 特別受益の対象となる贈与・ならない贈与
特別受益に該当するのは、以下の遺贈・贈与です(民法903条1項)。
- 1. すべての遺贈
- 2. 以下のいずれかに該当する贈与
-
婚姻のための贈与(例:持参金、嫁入り道具など)
養子縁組のための贈与(例:支度金、住居の準備費用など)
生計の資本としての贈与(例:生活費、不動産や車などの購入資金、学費、事業のための出資など)
ただし、婚姻・養子縁組・生活に関する贈与に当てはまりそうな場合でも、特別受益に当たらないと解される贈与もあります。
たとえば、生活費や学費を援助するためにされた親からの贈与であっても、扶養義務の範囲として妥当な金額の贈与であれば、特別受益には当たらないと解されています。
また、結納金や挙式費用などの贈与は、結婚「後」の生活を支える持参金や嫁入り道具に比べ結婚「後」の生活のためのものですらないため、結婚に関連してはいるもののやはり原則として特別受益には該当しません。
贈与(死因贈与・生前贈与)が特別受益に当たるかどうかの判断基準は、明文に定めがあっても曖昧な部分があるので、弁護士にご確認ください。
2 特別受益者がいる場合における相続分の計算の考え方
特別受益者がいる場合、特別受益の金額を相続財産に「持ち戻す」という考え方により、各相続人の相続分が計算されます。
⑴ 特別受益の「持ち戻し」とは?
特別受益の「持ち戻し」計算は、大まかに以下の考え方によって行われます。
- 特別受益の金額を相続財産に加算したうえで、各相続人の相続分を計算する
- 特別受益のある相続人の相続分は、上で計算された相続分から特別受益を控除した金額とする
特別受益の金額を相続財産に加算して法定相続分を計算(持ち戻し)することで、特別受益のある相続人の相続分は少なめに、そうでない相続人の相続分は多めに調整され、相続人間の公平が図られるのです。
⑵ 相続分の計算の「持ち戻し」に期間制限はない
相続分の計算においては、特別受益の「持ち戻し」を行う場合、持ち戻しの対象となる贈与については、期間の制限がありません。
したがって、たとえ30年前、40年前といった遠い昔に行われた生前贈与であっても、特別受益に該当する限りは、持ち戻し計算の対象となります。
ただし、それほど昔に行われた生前贈与の事実を、相続人自身が証拠を挙げて立証することは難しいため、生前贈与に関する調査などを弁護士に依頼することをお勧めいたします。
⑶ 「持ち戻し」は被相続人の意思表示で免除できる
特別受益の「持ち戻し」は、被相続人の意思表示によって、全部または一部を免除することが認められています(民法903条3項)。
たとえば遺言書の中で、特別受益に当たる贈与を摘示して「持ち戻しを免除する」と記載してあれば、相続分の計算において持ち戻し計算は行われません。
3 遺留分計算時の特別受益の「持ち戻し」
特別受益の「持ち戻し」は、遺留分を計算する際にも行われます。
ただし、遺留分計算における特別受益の「持ち戻し」は、以下のとおり、ここまでご説明した相続分計算の場合とは一部異なるルールが適用されることに注意しましょう。
⑴ 民法改正で「持ち戻し」の期間制限が新設
2019年7月1日施行の改正相続法により、「遺留分計算における」特別受益の持ち戻しには、「相続開始前10年間」という期間制限が新設されました(民法1044条1項、3項)。
改正前の旧民法では、「遺留分計算における」特別受益の持ち戻しは期間無制限とされていましたが、法改正によって新たに期間制限が設けられたことになります(ただし、民法改正前に開始した相続には適用されません)。
前述のとおり、「相続分計算における」特別受益の持ち戻しは、引き続き期間無制限です。
したがって、相続分計算時の特別受益の持ち戻しと、遺留分計算時の特別受益の持ち戻しは、期間制限の有無という点で異なっています。
⑵ 持ち戻しの免除は認められない
遺留分の計算においては、相続分の計算の場合とは異なり、被相続人の意思表示による特別受益の持ち戻しの免除は認められません。
遺留分は、被相続人の意思にかかわらず、相続人の相続権を最低限保障する制度です。
したがって、被相続人の意思表示による特別受益の持ち戻しの免除を認めれば、被相続人の意思により、遺留分を操作する余地を与えることになりかねず、ひいては遺留分制度の趣旨に反するため、適用がないものとされています。
⑶ 遺留分では法定相続人以外に対する遺贈・贈与も「持ち戻し」の対象
遺留分侵害額請求は法定相続人以外に対しても行い得ることから、遺留分計算における「持ち戻し」は、法定相続人以外に対する遺贈・贈与についても行われます(民法1044条1項)。
ただし、法定相続人に対する生前贈与の持ち戻しが相続開始から10年間遡るのに対して、法定相続人「以外の者」に対する生前贈与の持ち戻しは、相続開始前1年間に行われたものに限られます。
4 特別受益に関するよくある質問
生命保険金は特別受益に当たる?
被相続人がかけた生命保険の受取人に、一部の相続人のみが指定されていることはよくあります。
しかし、生命保険金は、受取人が固有の請求権を取得するものであって、被相続人から受取人に対する贈与ではありません。
したがって、原則として生命保険金は特別受益には該当しません。
ただし、最高裁の判例上、保険金受取人である相続人と他の共同相続人の間に生じる不公平が、特別受益制度の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存在する場合には、保険金請求権が特別受益に準じて持ち戻しの対象になると解されています(最高裁平成16年10月29日決定)。
上記の特段の事情の有無は、以下の事情を総合的に考慮して判断されます。
- 保険金額
- 保険金額が遺産の総額に占める比率
- 被相続人の同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど、受取人や他の相続人と被相続人の関係
- 各相続人の生活実態 など
もし生前の被相続人との関係性の深さに比べて、あまりにも多額の生命保険金を受け取る相続人がいる場合には、生命保険金が特別受益に該当する可能性を検討できるでしょう。
特別受益に当たる贈与は返さなければならない?
特別受益の持ち戻し計算を行った結果、特別受益者の相続分がマイナスになってしまうケースがあります。
このような特別受益者を「超過特別受益者」といいます。
超過特別受益者は、追加で遺産を相続することはできませんが(民法903条2項)、すでに受けた特別受益を返還する必要はありません。
ただし、特別受益に当たる遺贈・贈与によって、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求により、他の相続人に対して金銭の支払い義務を負う可能性があります。
特別受益者が相続放棄をした場合はどうする?
特別受益者である相続人が相続放棄をした場合、その者ははじめから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。
特別受益者となり得るのは法定相続人のみです。したがって、相続放棄によって相続人ではなくなった人が過去に受けた贈与については、もはや特別受益が問題になることは「原則として」ありません。
ただし、特定の(推定)相続人が被相続人の生前に、多額の特別受益を受けつつ、相続開始後に相続放棄した場合、持ち戻しができないことにより、あまりにも不合理な結果が生じることがあります。
その場合、その特別受益を得た者は、さかのぼって相続人ではなくなるので、当該特別受益対象行為を遺留分侵害額請求の対象とする方法や、同行為に対する詐害行為取消請求権の行使等を検討することになります。
特別受益を証明する証拠がない場合はどうすればいい?
特別受益に該当しそうな生前贈与や遺贈を受けていても、当然、特別受益を否定する相続人もいるでしょう。もし、遺産分割協議で特別受益について合意に至らなければ、遺産分割調停に持ち込むことになります。
調停は、あくまでも話し合いの場であり、こちら側の特別受益の主張を相手が認めれば合意できるでしょう。しかし、遺産分割協議で特別受益を認めなかった相手が、そう簡単に認めるとは考え難いです。
特別受益を主張する側には立証責任があり、できるだけ、証拠を揃え、特別受益について立証しなければなりません。
調停でも合意に至らなければ、審判へと移行します。しかし、もし特別受益が事実であったとしても、特別受益についての証拠がなく証明できなければ、残念ながら主張は認められません。裁判所に特別受益を認めてもらうには、証拠を提示して裁判所に証明する必要があるのです。
5 特別受益に関する紛争を防止するための対策
特別受益は、遺産分割協議・調停において、大きな揉め事の種になってしまう可能性があります。
もし特別受益に該当する遺贈・贈与が存在する場合には、生前に以下の対策をとって紛争を予防しましょう。
⑴ 遺言書の中で持ち戻しの免除の意思表示をしておく
前述した通り、相続分の計算における特別受益の持ち戻しは、被相続人の意思表示によって免除することが可能です(民法903条3項)。
そのため、遺言書の中で持ち戻しの免除の意思表示を行えば、相続人間における特別受益に関する紛争を発生させないようにすることができます。
遺言書において持ち戻し免除の意思表示をする際には、どの遺贈・贈与について免除を行うのかを明確に記載しなければなりません。
後のトラブルを防止するために、遺言書を作成する際には弁護士にご相談ください。
⑵ 生前贈与をする際には遺留分に配慮する
遺留分の計算における特別受益の持ち戻しは、被相続人の意思表示によって免除することができません。
そのため、特定の相続人に対して高額の生前贈与をした場合には、遺留分侵害額請求による相続人同士の紛争が生ずるリスクが高まります。
生前贈与を行う際には、極力他の相続人の遺留分を侵害しないように金額を調整して、紛争を防止しましょう。
⑶ 弁護士に遺産分割協議の調整を依頼する
実際の相続において特別受益が問題となった場合には、できる限り遺産分割協議によって解決することが望ましいと言えます。
そのためには、相続人それぞれの意見や希望をバランスよく調整することが大切です。
弁護士にご相談いただければ、適切な遺産分割協議によって、特別受益の処理についての合意を実現できる可能性が高まり、紛争の迅速・円満な解決に繋がります。
相続に精通した弁護士であれば、遺産分割協議において、相続人全員が納得しうる当事者としての観点を大切にしつつ、相続人全員と丁寧にコミュニケーションをとり、第三者的な視点から遺産分割協議を妥結へと導くことができます。
遺産分割において特別受益が問題となっている場合は、お早めにご相談ください。
法定後見制度(後見・保佐・補助)とは 代襲相続で起こりやすいトラブルと対処法